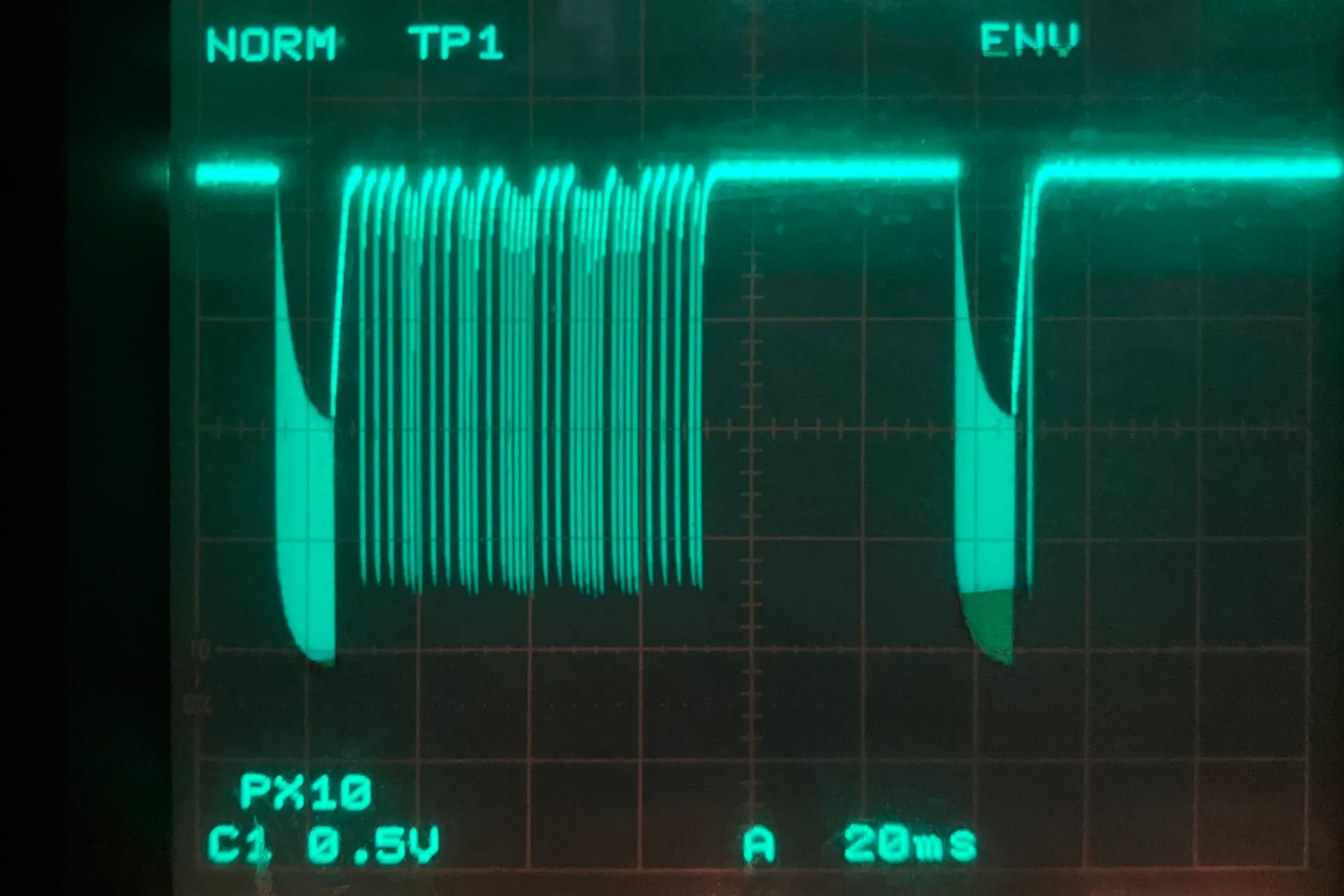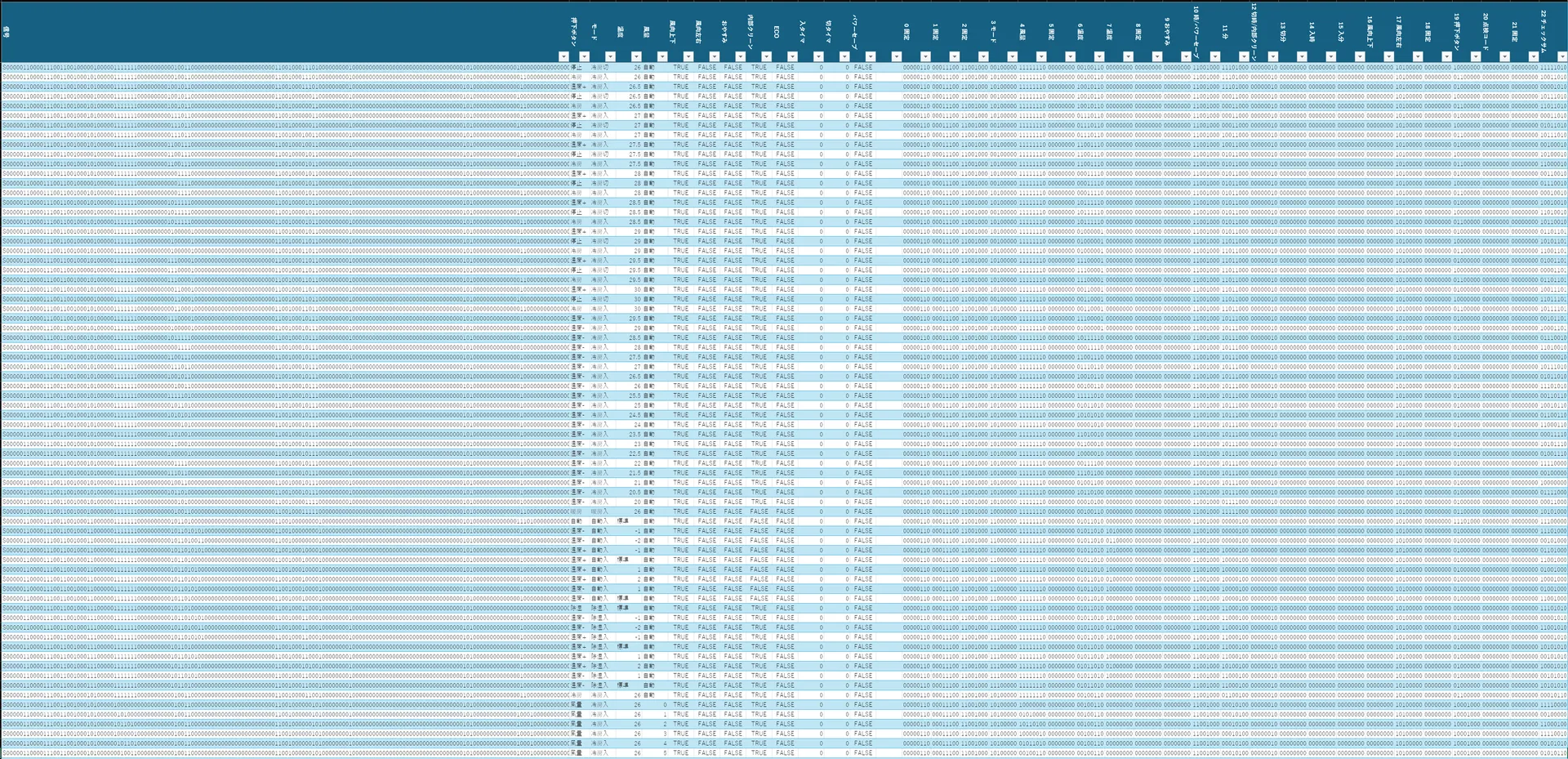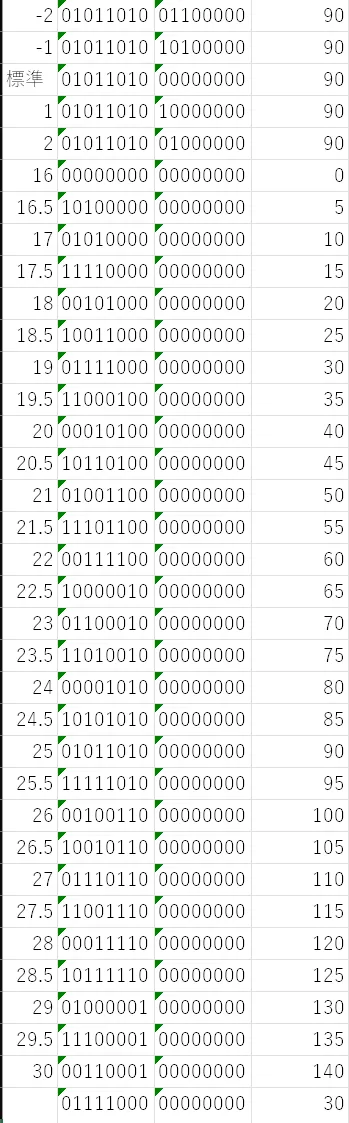ESP32で任意の赤外線リモコン信号を投げられるサーバを作ってみた
人間が生存可能な空間を生成するためにはエアコンが欠かせないわが国であるが、長時間出かけるときにもつけっぱなしというわけにはいかない(短時間であればつけっぱなしのほうが効率的なことはある)。しかし、帰宅してから電源を入れていては、部屋が人間の存在できる環境になるまでに時間がかかってしまう。帰宅時間がある程度予測できるのならタイマを設定しておけばよいが、大学生はいつ帰れるのか分からないがち。イマドキのエアコンであれば、インターネットに繋げて外出先からアプリで操作できるようなものもあるが、自室で使っているエアコンは最低限の機能のもので、そんな大層な機能はついていない。
そこで、遠隔操作でリモコンの赤外線信号を発することのできる装置を自作することにした。SwitchBotなど似たような既製品はないこともないが、この手の製品はNAT越えまで面倒を見てしまっていたりアプリから指示を出す前提だったりで、VPN経由でシンプルにWeb APIを叩くという使い方には向かないことが多い。この点はエアコンそのものに遠隔操作機能がついていても同様であり、多くの場合その複雑さゆえ信頼性も低い。また、材料は手持ちや工研に転がっているもので済むので作ったほうが安い。
設計指針
フロントエンドは常時起動PC(NASやWoLサーバに使用)で動作するWeb UIとする。PCとマイコンの間で通信し、マイコンから赤外線信号を発する。
PCとマイコンの間の通信は、LAN経由のHTTP APIとする。どうせ電源を取るのにUSBで繋ぐのでUARTで投げつけることも考えたが、Windowsでシリアルポートを扱うのは面倒なのでやめた。通信内容は送信したいビット列を送りつけるものとする。エアコンの設定を送りつけ、それに対応するビット列をマイコンの中に格納しておいて生成することも考えられるが、面倒なうえに柔軟性も欠くので却下。
マイコンはLAN接続ができる必要があるので、簡単にWi-Fiが利用できるESP32を使う。有線LANも頑張れば使えるらしいけど頑張らなきゃ使えない。Wi-Fiだけでなく、Remote Control Transceiver (RMT)という赤外線リモコン信号の送受信に特化したモジュールも搭載されている。
Web UIは使い慣れたBunで構成する。Webサーバ機能を内蔵しているため簡単なWebサービスを作るのには都合がよく、すでにWoLサーバで利用している。Bunでは容易にFFIができるため、簡単にシリアルポートを叩けるWin32 APIか何かがあれば嬉しかったが、残念ながらなさそうだった。
以前やったようにイヤホンジャックから音声として波形を直接出力すればマイコンが不要になるなども考えはしたが、後述するような搬送波を乗せるには周波数が足りるか怪しいことや、バックエンドから任意の音声を再生するのはブラウザと比べて面倒であることから、採用しなかった。
赤外線リモコンの形式
赤外線はそこらじゅうに溢れているので、単にHIGH/LOWをLEDのオン/オフに変換して世界に放っても信号として識別することはできない。赤外線リモコンでは、HIGHを点灯ではなく特定の周波数での点滅(矩形波)にし、受信側もその周波数でフィルタをかけることで、通信が成立している。振幅偏移変調(ASK)の一種のオンオフ変調(OOK)であり、振幅変調(AM)のデジタル版のようである。この特定の周波数で点滅する信号を搬送波と呼ぶ。搬送波の矩形波の周波数は38 kHzが使われることが多いらしい。また、デューティー比は1/3程度が一般的らしいが、状況によっては変えたほうが到達距離が伸びることもあるっぽい。
ここまではどの赤外線リモコンでも同じだが、開始、終了の目印となる信号や、データの0/1と信号のHIGH/LOWとの対応などはいくつかの形式が存在する。詳細は先人の記事を参照されたい。HIGHの部分が線ではなく塗り潰されているのは搬送波が乗っていることを表現していると思われ、実際、破壊しても困らない照明のリモコンを分解してLEDの電圧をオシロスコープで観測したところ、そのように見えた。ついでにこのリモコンが送信しているデータの形式を調べたところ、典型的なNEC形式だった。
送信器
ビット列を渡すことでそのまま送信できるようにするのは先述した通りであるが、照明のリモコンでは搬送波が33.5 kHzほどと標準的な値ではなかったため、搬送波の周波数やデューティ比も決め打ちではなく指定できるようにする。形式は今のところNEC形式決め打ちだが、その気になれば容易に他の形式にも対応できるようにする。
RMT
ESP32のArduino環境ではRMT向けにも簡略化されたAPIが提供されているが、以前述べたようにv2系とv3系とで使い勝手が異なり、また、PlatformIOそのままでは古いv2系が使われてしまうため、v3系を使うには細工が必要になる。
v2, v3問わずArduino-ESP32の公式ドキュメントにはRMTに関する情報はほぼ無いが、スケッチ例はv2ではなんだか取っ付きにくいものしかない一方で、v3ではいくらか増えたり読みやすくなったりしている。どちらもソースコード上のコメントから情報を得られるほか、基本的な概念についてはESP-IDFのドキュメントが参考になる。
APIの使い心地は全体的にv3のほうが良い。チャンネルの識別に謎のオブジェクトではなくピン番号を使えるようになった。RMTの時間単位であるTickの設定において、1Tickの長さには制約があるが、v2では要求したTick長が使えない場合は実際のTick長は勝手に決められ、返り値で実際のTickが返されていたのに対し、v3では要求したTickが使えない場合は初期化に失敗する(falseが返る)ようになった。また、搬送波の設定において、v2ではHIGHとLOWのクロック数(?)をそれぞれ計算して指定する必要があったのに対し、v3では周波数とデューティ比を指定できるようになった。その他のブロック数(?)などの定数も使いやすい形で定義されるようになった。途中でv3に切り替えたため、その時のコミット間差分を見ると分かりやすいかもしれない。
RMTでは、1ビットに対応する波形をHIGH/LOWの継続時間(Tick数)の形式で保持するRMTシンボルを定義し、これの配列を渡すことでその波形に予め指定した搬送波が載ったものがピンから出力される。同時にシンボル数も渡す必要があるが、いちいちsizeofするのはかっこ悪いので、文字列をパースする時に同時に数えておくようにし、配列と要素数の構造体として保持するようにした。そもそも配列をあらかじめ大きめに確保している場合、sizeofでは(中身の入っている)要素数を知ることはできないことに後から気づいた。
なお、搬送波について設定するrmtSetCarrier関数に罠があり、ソースコードのコメントにはcarrier_levelがtrueで「polarity level」が「positive」、つまりHIGHで波が出ると書いてあるが、実装を見るとこれがそのままpolarity_active_lowに渡されており、説明が逆になっている。通常の赤外線リモコンの信号を出す場合はfalseを渡す必要がある。
Wi-Fi接続
IPアドレスを固定する運用はあまりしたくないためDHCPで取得するが、これに時間がかかることがよくある。運用を初めたら再起動をかけることはあまりないと思われるが、検証中はいちいち待ちたくない。そこで、取得したIPアドレスを再起動後も保持するようにし、まずはそのアドレスで接続を試みるようにした。また、DHCP取得が遅い時は再起動するとすぐに繋がることが多いため、一定時間内に接続できなかった場合は再起動をかけるようにした。IPアドレスを固定しないため、PC側から名前解決ができるよう、mDNSも設定しておいた。
HTTPサーバ
WebサーバにはArduino-ESP32同梱のWebServer.hを使った。サードパーティのライブラリにESPAsyncWebServer.hなるものもあり、こちらも試してみたが、今回のような単純な用途ではあまり違いがないように感じた。なお、PlatformIO標準の古いArduino-ESP32ではESPAsyncWebServer.hは古いものしか使えないようである。Arduino-ESP32の最新版を使おうと思ったきっかけがこれだった。
リクエストの形式は、POSTでボディに情報を乗せるのではなく、GETでURLのパラメータを使ってデータや搬送波の設定を受け取るようにした。パースが楽なのと、curl等で簡単にテストができるためである(POSTもできなくはないが)。データは今のところ0と1で時系列順にした文字列で受け取るようにしているが、16進数に対応したり、ビット順、バイト順の指定をできるようにしてもよいかもしれない。
ハードウェア
赤外線LEDは工研に大量に転がっていたものを使ったが、型番が不明で仕様が分からなかったため、秋月で売っていて見た目の近いOSIR5113Aの数値を参考にすることにした。とりあえずGPIO直結で連続点灯の上限である25 mAが流れるように抵抗を噛ませ、データが単純である照明の信号を用いて試験したところ、照明のすぐ近くであれば反応したが、離れると機能しなかった。到達距離を伸ばすためには、数を増やしたり電流を増やしたりする必要がある。
ひとまず数を増やす。USBの5 V電源をそのまま使うことにすると、順方向電圧は1.25 Vのため、3本直列にすることができる。同じ本数ならできるだけ直列にしたほうが全体の電流も抵抗で捨てる電力も少なくて済む。これでは電圧も電流もGPIO直結では不足するため、MOSFET等でスイッチングする必要がある。ESP32のロジック電圧は3.3 Vのため、LEDを駆動するMOSFETも3.3 Vでオンになってもらう必要がある。以前使った都合のいいMOSFETは在庫が尽きてしまっていたため困っていたが、秋月で安売りされていたモータドライバ(と言いつつHブリッジとかではなくただのMOSFET)のDRV777がちょうど使えた。モータドライバはこれに限らず3.3 Vで使えることが多いので、3.3 Vで動くスイッチング素子がほしい場合は、MOSFET単品ではなくモータドライバを探す手もあることを学んだ。
電流は既に上限なので増やせないと見せかけて、LEDはパルス駆動であれば連続点灯よりも大きな電流を流すことができる。この電流はパルス幅とデューティ比によって決まるようで、パルス幅は瞬間的な最大温度、デューティ比は平均的な発熱量に影響すると思われる。たとえば、1 ms光らせて9 ms消すのを10回くり返すのと、10 ms光らせて90 ms消すのとでは、平均的な発熱量は同じだが、後者のほうが最大温度が高くなる、ような気がする。まずはデューティ比によって放熱能力に応じた制限がかかり、さらに周波数が低い(パルス幅が長い)と1回のパルスでの温度上昇も問題になり耐熱に応じた制限がかかる、という印象である。
永遠に搬送波を出し続けるわけではないため、搬送波のデューティ比と周波数をもとに計算すると保守的になりすぎると思われる。まず、パルス幅について、最も点灯時間が長いかつ見かけ上のデューティ比が大きい、開始信号における点灯時間(1/3 × 16 × 562 μs ≃ 3 ms)を考慮する。実際には連続点灯ではないため、これより余裕がある。次に、デューティ比について、すべて1だった場合の値(1/3 × 1/2 = 1/6)を考慮することにする。実際には開始信号(1/3 × 2/3 = 2/9)もあるので若干大きくなるが、0(1/3 × 1/4 = 1/8)も混ざることを考えると多少大きくても問題ないと思われる。
この値での電流値をデータシートで確認してそれを流せばよい、といきたいところだが、データシートにはパルス幅10 ms、デューティ比1/10での値しか載っていない。パルス幅はともかく、デューティ比は1/10より大きいため、この電流値そのままでは大きすぎる可能性が高い。そこで、他のLEDのデータシートからパルス幅とデューティ比と電流との関係を調べてみることにする。
パルス幅と電流の関係がグラフで示されている製品では、デューティ比固定の線を引いているものと周波数固定の線を引いているものとがあった。周波数固定の線を引いているものでは、パルス幅と電流の関係が両対数グラフで直線になっていた。デューティ比固定の線を引いているものは両対数グラフでないものが多く変な曲線になっていたが、両対数グラフのものでは、周波数が一定になる点を読み取っていくと直線になりそうな雰囲気だった。横軸がデューティ比でパルス幅固定の線を引いているものもあり、これは周波数を考慮していないようだが、同じく両対数グラフで直線になっていた。同じデューティ比でパルス幅や周波数を変えた場合の変化は、まったくないものも傾きが変わるものもあるが、変わる場合はパルス幅が短いほど電流が大きくなるようなので、パルス幅がデータシートの10 msより短い今回は無視しても余裕が増えるだけだと判断した。
周波数を固定すればパルス幅はデューティ比に比例するため、横軸をデューティ比、縦軸を電流とした両対数グラフで(1, 25 mA)と(1/10, 100 mA)の2点を結び、デューティ比1/6における電流を求めたところ、約74 mAとなった。電源電圧5 Vで、LEDをなるべく多く3本直列とすると順方向電圧は3.75 Vなので、電流制限抵抗は約18 Ωとなった。これは余裕をもった値であるため、在庫がある中で小さい側の15 Ωを使うことにした。使っているデータシート自体当てずっぽうなので多少雑でも今更である。
この電流と数であれば、部屋の端からでも照明を操作できるようになった。また、連続である程度送信してもLEDが燃えたり性能が低下したりはしていないようだった。なお、電源として使うUSB 2.0の電流は500 mAまでなので、やろうと思えば3直列を6並列の18本までLEDをつけられる。
リモコン解析
エアコンのリモコンがどのような形式で通信しているのかを調べる必要がある。エアコンのリモコンは壊したくないため、赤外線として送信された信号を受信して解読する。オタクが腐らせていた赤外線受信器OSRB38C9AA(Active Lowなので注意)を借り、出力をオシロスコープで観測してみたところ、開始、終了の信号と、0/1とHIGH/LOWの対応はNEC形式と同じであり、データ長のみ拡張されて23バイトになっていることが分かった。
データの中身を読み取る必要があるが、この長さではオシロの画面から目視で読み取るというのは難しい。そこで、Arduinoを用いて受信器の信号を0/1のビット列に変換できるようにした。色々な方式に対応しようとすると面倒になるが、NEC形式と決め打ちすればかなり簡単にできる。終了信号もパルスなので最終ビットまで立ち下がりエッジの間隔を見るだけで済み、あとは適当な時間経ったら終了と見なすことができる。RMTは受信にも対応しているようだが、使い方を調べることを考えたらこちらのほうが早い。
データが長いため、押したボタンだけを送信しているわけではなく、リモコン側が状態を保持していて毎度全て送信している方式であることが予想される。受信した信号のビット列と設定されていた状態をまとめる表を作成し、設定を網羅するように操作してデータを集めた。ビット列をバイトごとに区切り、設定と対応するバイトを探し出し、当該行をコピーしてExcelの「重複の削除」を使うことでビット列と設定との対応を得ることができた。
温度はリモコン上では0.5 °C刻みだが、データ上では0.1 °C刻みだった。また、風量はリモコン上では6段階だが、データ上はなんと100段階だった。どちらも変化を測定する術がないため、リモコンから送信され得ない値を送信した場合の本体の挙動は謎である。
途中ランダムに見える部分があり、受信器の不具合かと思ったが、どうやら時刻を保持しているらしいことが分かった。リモコンには時刻設定の機能はなく、単に電池を入れてからの時間かとも思ったが、しっかり時と分に分かれていて謎である。「待つ」以外に変化させる手段がないためサンプル数が限られるが、50台が上限っぽいので「分」だろうと当てをつけることができた。さらに、タイマの情報も「時間」ではなく「時刻」で送信されていた。
状態の送信のほかに、そのときの押下ボタンも送信されていたが、この情報はほぼ使われておらず、状態が優先される。たとえばモードを暖房、ボタンを冷房としても暖房になる。冷房/除湿後の内部クリーンや、解凍洗浄の開始のみボタンの情報が考慮されるようだった。
また、最終バイトのチェックサムと思われるものについて、変化したバイトと最終バイトの変わり方の対応から、各バイトのビットごとのXORだろうと予測したが、なぜか合わずに一定のずれ方をした。結果から言えば、先頭2バイトは無関係で、3バイト目以降のXORを取ると一致した。もとのNEC形式では先頭2バイトはカスタマコードなので、データ部のみのXORと考えれば説明はつく。
Web UI
ひとまずテスト用にすべてのパラメータを直打ちしてビット列を生成、送信できるWeb UIを作成した。同じリポジトリに解析結果のまとめも置いてある。Windows環境だとmDNSの解決が遅いことがあるため、環境変数ページを表示した時点でBUN_CONFIG_DNS_TIME_TO_LIVE_SECONDSを24時間ほどに設定したうえで、最初にBun.dns.prefetch()でキャッシュを生成しておくことで、毎日使う分には解決待ちを発生させないようにしている。Bun.dns.prefetch()を呼んでおくことで、送信ボタンを押すまでの間に名前解決させておくようにした。
動作確認
絵面は頼りないが、ここからESP32にリクエストが送られ、エアコンが指示した通りに反応することを確認できた。本物のリモコンの搬送波の周波数とデューティ比は不明だが、標準的らしい38 kHz、1/3でとりあえず機能した。
あとがき
自分で作ればアプリとかサ終とか気にせず好きなように使えるので、もしIoT対応エアコンだったとしても自作する価値はあるかもしれない。対応エアコンと異なる点として、エアコンから運転状態や室温などの情報を受け取ることができず、正常に送信できているかや、エアコンを使う必要がある状態かなどが分からない。温度センサを用意するなどの対策が考えられるが、そこまでやるかは未定である。
また、フロントエンドのUIはテスト用のままであり、リモコンを模したものなども作りたいところだが、今のままでもすべての機能は利用できるため放置している。最後に送信した状態を保持したり、現在時刻がちゃんと現在時刻になるようにするくらいはしてもいいかもしれない。
まだ遠隔操作できるエアコンという文明に慣れておらず、帰宅前に操作するのを忘れがちなまま、夏が終わってしまった。一応、帰宅してから自室の冷房を入れ、24時間空調(いぬがいるため)の居間で待機するという使いかたはよくした。冬は多少寒かったところで生命に関わるほどにはならないのでさらに意識が低くなっている。